歴史新聞、本日4月9日は何が起こった日!?
今日は歴史上で何が起こった日なのかを新聞のように報道します。
トピック 『後醍醐天皇、隠岐を脱出!船上山に御旗を掲げ、倒幕再起の狼煙上がる!「朕、未だ諦めず」――流刑の帝、反撃に転ず!』

元弘三年/正慶二年 閏二月二十四日(新暦:1333年4月9日)
信じがたい大逆転――
鎌倉幕府により隠岐島へと遠流されていた後醍醐天皇が、本日、密かに島を脱出し、伯耆国・船上山へと入山されたとの報が飛び込んできた!
先帝にして、討幕を夢見て、「流された帝」が、再び剣を取り、天の意志を掲げて御旗を立てたのだ。
[流刑の地・隠岐にて水面下の計画が進行]
元弘の乱により幕府に敗れ、1332年に隠岐へと配流されていた後醍醐天皇。
しかしその間、近臣・名和長年らが周囲を密かに整え、隠岐の漁民の協力を得て、今月初め、ついに夜陰に乗じて船で脱出。
そして本日、伯耆国の船上山に入られ、そこに仮の御所を構えたとのこと。
目撃者によれば、天皇は御旗を掲げてこう仰せられたという。
「この国を正すのは、いまこの時をおいて他にない」
「朕は決して倒れぬ。民のために、再び立つ!」
[山陰一帯に広がる支持の波――地元武士団が続々集結]
すでに、名和長年・南条時光ら伯耆・因幡の豪族たちが馳せ参じ、船上山の麓には数千の兵が集結中。
これにより、天皇側の軍事力は再び形を成しつつあり、周辺の守護・地頭たちも態度を揺らし始めている。
農民の間でも「やはり天子様には何かがある」と、天皇再臨の奇跡を讃える声が相次いでいる。
[幕府大混乱! 六波羅探題、緊急招集か]

この報を受けて、京に本陣を構える**六波羅探題(北条仲時・時益)**は大慌て。
「追討のための大軍編成」を準備中とされ、早ければ数日中に出兵の構え。
だが、関西一帯ではすでに倒幕の機運が高まっており、鎌倉では足利高氏(のちの尊氏)を司令官に後醍醐帝の追討軍が慌ただしく編成されているようだ。
だが、後醍醐帝に弓を引くことに躊躇する御家人たちもいるとの情報もある。
このときはまだ、御家人筆頭の足利家が幕府を裏切ることになろうとは誰も予想していなかった。
今、幕府の足元は、揺れている。
[帝、再び「天子」となる日]
後醍醐天皇――
かつて「異端の帝」と囁かれ、失意の中に追いやられたその御方が、
流刑地より這い上がり、ふたたび民を救わんと立ち上がった。
剣ではなく、信念を。
軍馬ではなく、志を。
この船上山より、新たな時代の風が吹き始めているのかもしれない――。
【注意】、あくまでも歴史新聞報道で、当時の状況を再現した報道であり、現代の報道ではありません。

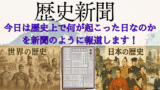
コメント