歴史新聞、本日4月7日は何が起こった日!?
今日は歴史上で何が起こった日なのかを新聞のように報道します。
トピック『幕臣 川路聖謨、割腹の末にピストル自決――幕府に殉じた男の最期』
慶応四年三月十五日(新暦1868年4月7日)
本日未明、一人の忠義の士が静かに生涯を閉じた。かつて幕府の外交の第一線で活躍し、数々の難局を乗り越えてきた名幕臣、**川路聖謨(かわじ としあきら)**が、自宅にて自ら命を絶った。68年の生涯の幕引きは、武士としての切腹であり、日本初とされるピストル自殺であった。
かつて、国を守るために交渉の場に立ち続けた男が、いま江戸城開城を目前にして、ひとり静かに幕府の終焉に殉じた。
[幕府のために生きた男]
川路は享和元年(1801年)、豊後日田の代官所の小屋で生まれた。最下級の役人から勘定奉行にまで昇り詰めた努力の人であり、幕府が外国勢力と渡り合う中で、最も信頼された人物のひとりであった。
嘉永6年(1853年)、ペリー来航の翌月に長崎に来航したロシアの使節プチャーチンとの交渉では、堂々たる態度と巧みな話術で対話を進め、ロシア側から「ヨーロッパでも珍しいほどのウィットと知性をそなえた人物」と称賛された。
翌年には日露和親条約を締結した。
その働きぶりは壮絶であった。彼の一日は午前2時起床、読書と書き物、夜明けとともに刀と槍の素振りを2000回ずつ。来客を迎え、10時に登城、17時まで城に詰め、帰宅後もまた来客の話を聞き、夕食後は読書と書き物を続け、深夜0時に就寝。睡眠時間はわずか2時間。
幕府のために働き続けた彼は、しかし運命のいたずらにより、やがて時代の波に呑まれていくことになる。
[安政の大獄、そして幕府崩壊へ]
川路は開明的な幕臣でありながら、将軍継嗣問題では一橋派につき、井伊直弼に睨まれる。結果、安政の大獄に連座し、長年勤め上げた職を追われた。
その後、幕末の動乱の中で幕府は次第に力を失い、ついに江戸無血開城の決断が下される。かつて日露和親条約をまとめあげ、幕府の未来を築こうとした男にとって、それはあまりに耐え難い現実だった。
「私をここまで育ててくれた幕府の恩義に、私はどう応えるべきか」
川路は考え抜いた。そして、武士の誇りをもって幕府とともに死ぬことを選んだ。
[壮絶な最期]
慶応四年三月十五日、川路は自宅で正座し、短刀を取り出す。すでに病で身体は満足に動かぬ状態であったが、武士の作法を守るべく、震える手で自らの腹に刃を突き立てた。
しかし、病に侵された身体では思うように切腹ができず、川路は拳銃を取り出し、自らの命を断った。
壮絶な最期だった。割腹と拳銃という二重の覚悟――その死に際して、彼の心には何が去来していたのだろうか。
[今、川路を想う]
川路聖謨は、武士として生き、幕府とともに死んだ。
だが、彼の足跡は決して消え去ることはない。彼がまとめあげた日露和親条約は、日本の歴史に刻まれ、彼が守ろうとした国は、新たな時代へと進んでいく。
68年の生涯を、誠実と忠義に捧げた男――その姿を、我々は決して忘れてはならない。
【注意】、あくまでも歴史新聞報道で、当時の状況を再現した報道であり、現代の報道ではありません。

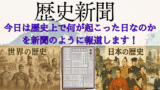
コメント