歴史新聞、本日4月3日は何が起こった日!?
今日は歴史上で何が起こった日なのかを新聞のように報道します。
トピック『武田家、ついに滅ぶ!――天目山に散った名門の誇り、勝頼公自刃、名門武田家、ここに潰える』

天正十年三月十二日(新暦1582年4月3日)
本日、甲斐国・天目山にて、武田家最後の当主・武田勝頼公が自刃されたとの報が入った。
勝頼公とその夫人・北条夫人、御子息・信勝さまも共に命を絶ち、ここに、名将・武田信玄を祖とする名門・武田宗家が滅亡するに至った。
戦国の荒波を疾走した甲斐の名家、その最期は、家臣の裏切りと時代の波に呑まれた哀しき悲劇であった。
[かつての覇者、信玄の遺産]

武田家といえば、甲斐・信濃を中心に広く影響力を持った名門中の名門。
中でも勝頼の父・武田信玄公は、「甲斐の虎」と称され、上杉謙信と五度に渡る川中島の戦いを繰り広げ、
その武略と統治力において、天下人・織田信長や徳川家康からも畏れられた存在であった。
信玄の「風林火山」の旗印――
「疾如風、徐如林、侵掠如火、不動如山」
その精神は、甲斐の兵すべてに浸透し、勇猛果敢な騎馬軍団は戦国最強と謳われた。
[勝頼公、孤高の将として戦うも…]
信玄の死後、家督を継いだ勝頼公。
武田家の威信を保つべく戦を重ね、織田・徳川連合に抗い続けた。
しかし、信玄の遺言により「家督は勝頼の嫡男・信勝に…」との声も囁かれ、勝頼公の正統性をめぐる陰が常につきまとった。
それでも勝頼公は耐えた。
長篠の戦で大敗を喫し、武田騎馬軍団が崩壊した後も、信濃・駿河を巡る地道な再興戦に全力を尽くした。
しかし、周囲は冷たかった。
家中には不満と陰謀が渦巻き、ついには重臣・木曾義昌、穴山梅雪らが離反。
家臣の裏切りと織田信長の圧倒的侵攻を前に、武田家の命運は風前の灯火となった。
[天目山の最期――炎の中、武士の誇り貫く]

追い詰められた勝頼公は、わずかな家臣とともに山間を逃れるも、
妻子とともに天目山・田野の地にて討たれる。
この時すでに勝頼公の手元には援軍も残されず、兵糧も尽き果て、もはや自刃の道しか残されていなかった。
「父の名に恥じず、堂々と果てよう」
「我が命より、武田の名こそ惜しむ」
その言葉を残し、勝頼公は愛妻・北条夫人とともに自刃。子息・信勝も同じく命を絶った。
家臣たちも次々と殉死し、その忠義に涙を禁じ得ぬ者も多い。
[地元民、嗚咽の声]
田野の里では、村人が残された武田家の旗を拾い上げ、
「これは誇りだ、どうか埋めてやってくれ」と語ったという。
一人の老農夫は涙を流しながら語る。
「若き頃、信玄公の馬の蹄の音を聞いた。
勝頼さまも、よう戦った…よう戦ったのにのう……」
[風は止まず、ただ旗だけが舞う]
武田家――
それは「恐怖の力」ではなく、「信義と地力」で地に根差した家であった。
信玄公の治世は仁政にして厳正、民は豊かに暮らし、兵は忠義に燃えた。
だが、時代は変わった。
織田の鉄砲と計略、裏切りと情報戦の嵐の中で、誠の力は声を失った。
武田勝頼公、若き将よ。
あなたは信玄の影に苦しみながらも、家を支え、生き抜いた。
どうか、父君と母君のもとで安らかに――
今、甲斐の空には、
誰もいなくなった城の上を、風が鳴いている。
そしてその風の中で、
「風林火山」の旗が、音もなく空に消えていった――。
[時代は変われど、敬愛は残る]
武田勝頼という名は、歴史書では「敗者」として記されるかもしれない。
だが、甲斐の民の中では、決して“愚か者”でも“暴君”でもなかった。
「お主が生き延びていたら、また甲斐は栄えておったろうに」
――ある老僧が、墓前に捧げた言葉
勝頼公の最期は、「忠義を尽くし、誇りを貫いて散った武士」の姿である。
その姿は、村の祠に、山の石に、そして人々の胸に、今も生きている。
【武田家滅亡後の続報です。】
勝頼の家臣たちはその後どうなったのか。
[土屋昌恒、壮烈なる最期]
まず名を挙げねばならぬは、**土屋昌恒**であろう。
勝頼公の最期に殉じ、わずか50余の兵で織田軍3000を迎え撃ち、壮絶な討死を遂げた。
「主君の首を敵に渡すことなかれ」
との気迫をもって奮戦し、死してその忠義を後世に刻んだ。
[小山田信茂、裏切りの果てに処刑]

一方で、家の命運を誤った者もいる。
**小山田信茂**は、勝頼公に「未完成の新府城を捨てて、岩殿城に来られよ。難攻不落の我が城にてお迎えします」と誘いながら、追い詰められた武田勝頼が、最後の希望を託して岩殿城に入ろうとした際、信茂は突如門を閉ざし、主君を拒絶――それは裏切り以外の何物でもなかった。
勝頼は落胆のうちに天目山へ向かい、家族とともに自刃。信茂はその後、織田信長のもとに出頭し、勝頼を見捨てたことで忠節を示したつもりであったが、信長の裁きは苛烈だった。「主君を裏切る者は、敵すら欺く」――信長は即座に信茂を捕え、その場で斬首。小山田家は一族郎党もろとも断絶された。
信茂の最期は、武士の忠義とは何かを後世に問う象徴ともなった。勝者の信長すら、裏切りをもって成り上がろうとする者を決して許さなかったのである。
[忠義か保身か――穴山梅雪、裏切りの代償]

甲斐武田家の名将・穴山梅雪は、信玄の側近として仕えた智勇兼備の武将であり、勝頼にとっては叔父にあたる重臣であった。だが、武田家が織田・徳川連合軍の侵攻にさらされると、梅雪は突如として織田方に寝返り、領地と命を守るために勝頼を見限った。
その裏切りにより、勝頼は信じられる味方を失い、天目山へと追い詰められてた。武田家の滅亡を早めた張本人として、梅雪の名は後世まで語り継がれることとなる。
しかし、梅雪の運命もまた、皮肉な形で終焉を迎える。武田滅亡後、織田信長より恩賞を受け、安堵された梅雪であったが――その直後、本能寺の変が勃発。明智光秀の謀反により信長が横死し、情勢は一変。徳川家康とともに堺から脱出する途中、梅雪は京都郊外で土民の襲撃を受け、非業の死を遂げた。
その死に様に、人々はこう囁いた。「忠義を捨てて得た命は、風に散る泡沫にすぎぬ」と。
【注意】、あくまでも歴史新聞報道で、当時の状況を再現した報道であり、現代の報道ではありません。

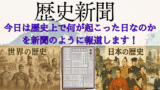
コメント