歴史新聞、本日3月25日は何が起こった日!?
今日は歴史上で何が起こった日なのかを新聞のように報道します。
トピック『東国の英雄、ここに散る――平将門、乱戦の中に討ち死に!――「この国を、民のために」夢破れし武士の魁』

天慶三年二月十四日(新暦:940年3月25日)
本日未明、関東を騒然とさせた承平・天慶の乱において、東国の雄・平将門公が戦死されたとの報が入りました。
将門公は、下総国の猿島郡北山(現在の茨城県坂東市・古河市一帯)に布陣し、わずか400の手勢で、約3,200人にも及ぶ追討軍――平貞盛・藤原秀郷の連合軍を迎え撃ちました。
戦況は極めて不利でありながらも、将門公は最後まで奮戦し続け、敵軍に囲まれる中で額に矢を受けて落命したと伝えられています。
その死は、ただの乱の終息ではなく、一人の男が夢見た「もうひとつの国」の終焉でもありました――。
[将門は“朝敵”にあらず――東国の民に慕われた「地の王」]
朝廷の命により、「謀反人」「逆賊」として追討された将門公ですが、関東の民の間では、その姿はまったく異なるものとして語られてきました。
将門公は、もともと同族との土地争いから戦に身を投じましたが、単なる領地争いの武士ではありませんでした。
彼が治めた地では、横暴な役人や国司の圧政を排し、村々に秩序をもたらし、庶民の暮らしを安定させたのです。
役人による不当な徴税、武力による略奪――そうした**「公」の名を借りた私利私欲の支配に苦しむ農民たちにとって、将門公こそが唯一の救いでした。**
村の水争いを公平に裁き、年貢を減らし、兵を民のために使う――その姿勢は、中央の貴族たちが決して見ぬ庶民の生活に、真っ直ぐ向き合うものでした。
ある常陸の農民はこう語っています。
「国府にどれだけ訴えても届かぬ声を、将門様だけは耳を傾けてくれた。田畑を守ってくれた。米俵が盗られずに済んだ。わしらにとっては“国の王”だったよ…」
そして、やがて将門公は自らを「新皇」と称しました。
この行為は、朝廷にとっては明確な「謀反」と映りましたが、実際には、中央政府の腐敗と無関心に見切りをつけ、東国のために東国の王が必要だと信じた将門公の、苦渋に満ちた決断だったのです。
それは「反逆」ではなく、血筋や格式ではなく、“民のためにある政治”を貫こうとした、もう一つの国家観、時代に先んじた、誠に悲壮な改革の志であったのではないでしょうか。
[最期の戦い――誇りとともに]
平将門公が最後の布陣を行ったのは、下総国猿島郡北山(現在の茨城県坂東市・古河市の一部)。
そこには、わずか400人の兵が集結していました。対するは、平貞盛と藤原秀郷の連合軍、約3,200人。
兵力差は実に8倍という圧倒的な不利な状況の中、将門公は一歩も退かず、静かに北山の地に馬を止めました。
だが、将門公はただ数に怯える男ではなかったのです。
この日、戦場には激しい北風が吹いており、将門公はこれを見てとると、風上に布陣。
当時の戦いはまず、弓矢の応酬から始まるのが常であり、風上に立つことは命運を左右する最初の鍵でした。
将門軍は風の力を背に、一直線に敵軍へ突撃。その勢いは凄まじく、たった400人の軍勢が、なんと約2,900人の敵を総崩れに近い状態へと追い込んだのです。
連合軍は精鋭の300人を残してほぼ壊滅でした。将門の戦術は完璧であり、勝利は目前に迫っていました――
しかし、その刹那、風が止みました。
それまで背中を押していた北風は、突如としてやみ、そして、南風が吹き始めたのです。
形勢は一転。今度は連合軍が風上に立ち、矢の雨を将門軍に向けて放ち始めました。
風向き一つで、戦局が覆される――それは運命のいたずらであったのか、それとも天が試練を与えたのか。
将門軍は必死に持ちこたえるも、少しずつ後退を余儀なくされました。
そしてそのとき――
強風にさらされた戦場で、将門公は一本の流れ矢に額を貫かれ、静かに馬上から崩れ落ちました。
駆け寄った家臣に、将門公は最期の言葉をこう残したと伝えられています。
「我が身は風に斃れようとも、志は風に乗りて未来へ届こう。
いずれこの地に、民のために立つ真の王が現れようぞ――」
将門の死と共に、承平天慶の乱は終結しましたが、
この一戦により、「武士の時代」が全国に知られることになるでしょう。
そしてきっと、武士の台頭を促し、やがて武家政権誕生の礎になるに違いありません。
将門公は敗れたかもしれません。
しかしその風のような一生は、千年、万年を超えてもなお、この地に吹き続けるでしょう。
[編集後記:千年早すぎた理想]
将門公の首は都に送られ、獄門に晒されるとのことです。
平将門――
その名は歴史の教科書に「朝敵」として記されるかもしれません。
だが、私たちは知っています。
彼は、民の命と暮らしのために剣を取り、命を賭して立ち上がった「時代の先を行きすぎた英雄」だったのだと。
たとえ歴史に敗れても、志は生きる。
関東の風の中に、今日も将門の夢が吹いています。
【注意】、あくまでも歴史新聞報道で、当時の状況を再現した報道であり、現代の報道ではありません。

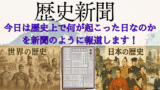
コメント