歴史新聞、本日3月23日は何が起こった日!?
今日は歴史上で何が起こった日なのかを新聞のように報道します。
トピック『日本の少年たち、ついにローマ教皇と謁見!――「遥かなる東の国より来たる使節団」、全欧州が称賛!』

天正十三年二月二十二日(西暦1585年3月23日)
本日、日本のキリシタン少年たち4名が、ローマ教皇グレゴリウス13世に公式謁見を果たした!
この歴史的な一歩は、はるか遠い東方の島国・ジパングと、ローマ教皇庁との間に架けられた“信仰の架け橋”として永く記憶されることであろう。
[誰がこの少年たちを送ったのか?]

この使節は、九州のキリシタン大名――大友義鎮(宗麟)、大村純忠、有馬晴信の三名によって、ヨーロッパに派遣された。
彼らの目的はただ一つ。
「教皇と諸王に敬意を表し、日本のキリスト教徒たちの存在とその信仰を伝えること」である。
発案・主導したのは、イエズス会の宣教師アレッサンドロ・バリニャーノ。
彼はこの旅を通して、教皇庁に日本への布教援助を要請し、ヨーロッパ諸国に日本の存在と信仰の真剣さを伝えようと考えたのだ。
[正使・副使の4人の少年たち、その素顔とは?]
- 正使:伊東マンショ
- 日向国(現・宮崎県)の伊東氏の血を引く武家の子弟。落ち着いた人格と教養で使節団のリーダー的存在。キリスト教名は「マンショ」。
- ローマでも特に礼儀正しい態度が高く評価された。 - 正使:千々石ミゲル
- 肥前国(現・長崎県)の千々石氏の出身。大村純忠の甥である。若くして熱心な信仰心と豊かな表現力で注目を集めた。
- キリスト教名は「ミゲル」。ヨーロッパの文化に強い関心を示し、異文化にも臆せず堂々と振る舞った。 - 副使:原マルチノ
- 肥前国出身。大村純忠の一族といわれる。明晰な頭脳と学問への関心が深く、通訳的な役割も担った。
- ラテン語の理解力に優れ、ヨーロッパの聖職者から「まるで我が修道士のようだ」と称賛された。 - 副使:中浦ジュリアン
- 肥前国中浦城主の子として生まれる。信仰への強い情熱と親しみやすい人柄で、ヨーロッパの貴族や修道士の間で人気を博した。
- ヴェネツィアでは人々から花束を贈られるなど、最も市民に愛された少年のひとり。
[旅路は命がけ!アジアからヨーロッパへ大冒険]
1582年1月、長崎から出発した使節団は、マカオ→インド(ゴア)→喜望峰→ポルトガルのリスボン→スペイン(マドリード)→ローマという壮大なルートを辿った。
途中、嵐や病、長期の滞在を挟みながら、実に3年の歳月をかけてローマの地に到達したのである。
スペインでは国王フェリペ2世に謁見し、日本の若者たちの知性と品格はヨーロッパ宮廷でも高く評価された。
[ローマ、少年使節に喝采!教皇より「黄金の拍車の騎士」授与!]

本日、ついにローマ教皇グレゴリウス13世に謁見。三大名からの書簡と贈り物を奉呈し、誠実な信仰と熱意をもって語った彼らの言葉に、教皇も深く感動したという。
使節団は、ローマ市民権を授与され、「黄金の拍車の騎士」に任命されるという破格の歓迎を受けた。
さらに、日本における神学校(セミナリオ)設立への教皇庁の援助が約束された。
[歴史が動く――東西の信仰が交わる瞬間]
この使節団の旅は、文化・言語・年齢・大陸を越えた“信仰の物語”である。
ヨーロッパにとって、極東の小国・日本からこれほど品位と敬虔さを備えた少年たちが訪れたことは、大きな驚きと感動を与えた。
そして今、ローマは問うている。
「日本は、神の恵みに選ばれた新しき地なのではないか?」と。
[編集後記]
十代の少年たちが、命を賭して踏みしめたこの旅路は、後世に語り継がれるであろう。
彼らが日本に帰る日、どれほどの希望と変化をもたらすのか。
その未来が、いま始まっている。
【注意】、あくまでも歴史新聞報道で、当時の状況を再現した報道であり、現代の報道ではありません。
#歴史 #新聞 #本日 #天正遣欧使節 #ローマ教皇

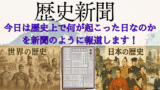
コメント