歴史新聞、本日4月2日は何が起こった日!?
今日は歴史上で何が起こった日なのかを新聞のように報道します。
今回は、藤原道長の娘である彰子が中宮になり、定子が皇后宮になったという記事ですが、一つの歴史新聞社が藤原道長寄りの記事を出したのに対し、定子寄りの記事を出した歴史新聞社もありますので、2社の記事を続けてご紹介します。
まずは藤原道長寄りの記事です。
トピック『彰子さま、中宮にご冊立!宮廷に新たな光、道長公の娘、ついに皇后の座へ!文と徳の華咲く時代の幕開け、文化の女君として期待高まる!』

長保二年二月二十五日(新暦1000年4月2日)
本日、ついに、藤原道長公のご息女・彰子さまが、中宮として正式にご冊立されました!
長らく女御として御所に仕えられていた彰子さまは、今日、晴れて正式な皇后の御位に昇られ、
そのご威容はまばゆいばかり。参内した貴族・女房たちは、口々に「新しい時代の扉が開かれた」と感嘆の声をあげております。
[道長公の政略、ここに結実]
彰子さまの父である藤原道長公は、今や左大臣として宮廷の中枢を担う人物である。
摂政・関白の座を持たぬまま、政の実権を握り、王家との結びつきを深めるその巧みな政略眼は、貴族たちから「御門の後見」とも称されております。
今回の冊立により、道長公は一条帝の外戚としての地位を確立し、将来の“皇太后の父”への道も見えはじめました。
いまや平安の世には、「道長を置いて語ることなし」との声も高まっております。
[文化の花咲く女院御所――「彰子サロン」注目集める]
中宮彰子さまのもとには、すでに紫式部、和泉式部、赤染衛門など、
当代随一の才女たちが女房として仕えており、御所はまさに文の都、才知の殿堂の様相を呈しています。
「中宮さまは御聡明で、物語を愛し、和歌を嗜み、書を深く学ばれておられます。
わたくしどもも仕えることが光栄でなりませぬ」
(女房・紫式部の証言)
この先、文学・芸術・学問を中心とした**“文化政治”の展開**に、貴族社会の期待が高まっております。
[二人の皇后、前例なき並立――だが宮廷は祝福一色!]

今回、すでに皇后であった**定子さまは「皇后宮」**と称され、
彰子さまが「中宮」として新たに立てられるという、**前例のない「二后並立」**の形がとられました。
しかし、宮中内外の反応は、若さと教養、そして藤原道長公という圧倒的な後見を得た彰子さまへの祝賀ムード一色!
今や「真の皇后はこちら」との声が貴族たちの間でも囁かれております。
[「時代の華、咲く」]
今回の中宮冊立は、道長公の勢力誇示に留まらず、文化と教養を重んじる政治の幕開けでもあります。
彰子さまは、単に皇后というだけでなく、
文学の興隆、宮廷文化の刷新、そして未来の国母としての期待を一身に背負う存在。
今後、この御方を中心に、平安京がどう輝きを放ってゆくのか――
平安の世はいま、まさに新しい光に照らされようとしています。
続いて、定子寄りの歴史新聞社の記事です。
トピック『「中宮」の座、奪われる!定子さま、涙の称号変更――「皇后宮」としてなお気高く!その影で蠢く道長の権力――これぞ策謀の世か!』
長保二年二月二十五日(新暦1000年4月2日)
本日、長らく一条天皇の御側で「中宮」として愛されてきた中宮・定子さまが、突如として「皇后宮」へと称号を改められるという異例の事態が発生した。
理由はただ一つ。
藤原道長の娘・彰子さまが、新たに中宮として冊立されたことによる「二后並立」の施策。
だがこれは、果たして天皇のご意志によるものなのか――
それとも、道長の権力欲が生み出した“静かな政変”ではなかろうか。
[天皇の寵愛、誰の目にも明らか――それでも退けられる理不尽]
定子さまといえば、一条天皇が若き日より深く慕われた御方。
その美しさと聡明さ、そして何よりも穏やかで気高いご性格は、
宮中の誰もが知るところである。
御子・敦康親王をご出産され、まぎれもなく正嫡の皇后。
そして文学をこよなく愛され、清少納言ら女房たちとともに文化の華を咲かせた御殿は、
今や多くの公家や女官たちにとって「心の拠り所」である。
それでもなお、この座を奪われる理由とは何か?
愛よりも血筋、誠よりも策略が重んじられる世となってしまったのか。
[道長の采配、正義か野心か?]
政の中枢を握る藤原道長公は、定子さまにとって叔父にあたる存在。
その道長公が、あえて姪である定子さまの座を押しのけ、自らの娘を皇后に据えた今回の決定――
そこには「忠義」よりも、「自己の家の繁栄」の色が濃く見え隠れする。
「天にあらば月にくらぶる道長の
影はこの世を照らすべきかは」
そう詠む者も出るほど、今、道長公の動きには民も貴族も警戒を抱きはじめている。
その采配は、国を照らす光か、それとも他の光を遮る陰か。
[定子さま、沈黙の美徳をもって宮に残る]
このたびの称号変更に際し、定子さまは一切の不満を口にされず、
ただ静かに「皇后宮」として御所に留まり、女房たちを励ましておられる。
ある女房は語る。
「中宮の名を失っても、定子さまの気品とご誠実は何ひとつ変わりませぬ。
天皇さまのお心が、今も変わらぬことを、わたくしどもは知っております」
[「称号は移ろえど、心は残る」]
中関白家の時代は終わった――そう囁く声もある。
だが、本当に終わったのは“権勢”であって、“真の皇后”の品位ではない。
道長殿よ。
娘を中宮に据えたことを“勝利”と思われるな。
人々の記憶に残るのは、誰が最も気高く、誠実で、天皇の心に寄り添ったかである。
この政の歪みに、やがて誰もが気づく時が来よう。
その時、京の民も、公卿たちも、こう語るであろう。
「名がどう変われど、真の皇后は定子さまだった」と。
【注意】、あくまでも歴史新聞報道で、当時の状況を再現した報道であり、現代の報道ではありません。

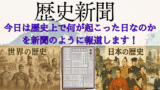
コメント