歴史新聞、本日4月12日は何が起こった日!?
今日は歴史上で何が起こった日なのかを新聞のように報道します。
トピック 『原城、ついに陥落――島原の乱、終焉す、炎と祈りの四ヶ月、37,000の命、散りぬ』
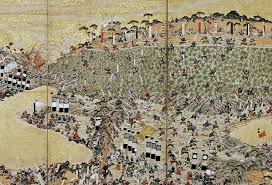
寛永十五年 二月二十八日(新暦:1638年4月12日)
本日早朝、激しい轟音とともに、原城が崩れ落ちた。
島原の乱――天草四郎を中心とした農民・キリシタンの一揆軍が籠もった最後の砦が、幕府軍の総攻撃によりついに落城。
約四ヶ月におよぶ凄惨な籠城戦は、37,000もの命とともに幕を閉じた。
だが、そこにあったのは“反乱”ではなく、信じるもののために立ち上がった名もなき人々の、魂の叫びであった。
[信仰と飢えと怒りが導いた決起――なぜ彼らは戦ったのか]

島原・天草地方は、豊臣政権下ではキリシタン大名による庇護のもと、多くの民が「デウスの教え」に心を寄せていた。
だが徳川幕府によるキリスト教禁制が強化され、領主の松倉勝家・寺沢堅高は重税と圧政で人々を容赦なく追い詰めた。
天災と飢饉が人々の暮らしを襲い、
信仰を捨てれば命が助かると脅され、
神を信じれば家を焼かれる――
祈ることすら罪とされ、食うことすら叶わぬ日々。
そうした中、**奇跡の少年――天草四郎時貞(益田四郎)**が現れた。
「われらが苦しむのは、人の罪にあらず。
神の試練に耐える者は、救われるであろう」
この言葉に民は立ち上がった。
飢えに苦しむ母たちが、
踏絵を拒んだ老人たちが、
明日を知らぬ子どもたちが、
皆ひとつの希望にすがり、原城へと集結したのである。
[「神の砦」となった原城、怒涛の籠城戦]
原城はかつての有馬氏の城であり、廃城となっていたが、
民と浪人らはわずか数週間で**“神の砦”へと再構築した。**
土を掘り、石を積み、祈りながら戦うための拠点が築かれた。
数千の人々が、雨風と飢え、そして幕府軍の大軍に囲まれながらも、耐え、歌い、祈り、生きた。
内部には「ミサ」が開かれ、子どもたちは「アヴェ・マリア」を歌い、
女たちは火打石で矢じりを磨き、老兵は十字を刻んだ木の槍を携えた。
「武器ではなく、信仰で戦う――」
それが、彼らの覚悟だった。
[幕府の怒り、火を吐く――12万人が城を包囲]
幕府はこれを許さなかった。
板倉重昌の戦死後、老中松平信綱が総大将として着陣。
延べ12万人ともされる幕府軍が原城を包囲し、弾薬・食料の補給路を完全に断った。
飢え、寒さ、病。
幕府は人ではなく、自然そのものを兵とした。
それでも、誰ひとり降伏せず。
「命を捨ててでも、信を守る」
それが、この城に生きる者すべての“約束”だった。
[そして最期の日――祈りの城、落つ]
二月二十八日(新暦4月12日)
明け方、城外から銃声と鬨の声が轟く。
幕府軍は四方から原城を攻め、堀を越え、塀を乗り越え、火を放った。
矢も弾も尽き、素手で抗う者もいた。
燃え盛る砦の中で、十字を握ったまま倒れた者もいた。
ある幕府兵の証言:
「敵とは思えぬ…
女も子も、なぜあれほど誇り高く死ねるのか…」
天草四郎は、討ち取られたとも、天へ昇ったとも伝わる。
その最期は定かではない。
だが、落城の刻――
原城のどこかで、確かに**“祈る声”が響いていた**と伝えられている。
[松平信綱、戦後処理に沈黙――“正義”はどこに?]

勝利を告げる鐘は鳴らなかった。
松平信綱は、「反乱鎮圧」として江戸に報告したが、
彼の表情は晴れなかったという。
「民を救えぬ政に、何の徳があろうか」
と、側近に語ったとも。
[我らを赦す神はあったか]
民が祈りの手を掲げたとき、
空は答えを返しただろうか。
神はそこにいたのだろうか。
だがひとつだけ確かに言えることがある――
原城に死した3万7千の魂は、
力ではなく“信”を抱いて倒れたということ。
祈りのために死んだ人々がいた国。
その事実を、我らは決して忘れてはならぬ。
彼らの名は歴史に残らずとも、
この日、この空に――
祈りの叫びは、永遠に刻まれた。
【注意】、あくまでも歴史新聞報道で、当時の状況を再現した報道であり、現代の報道ではありません。

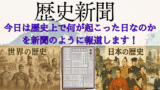
コメント